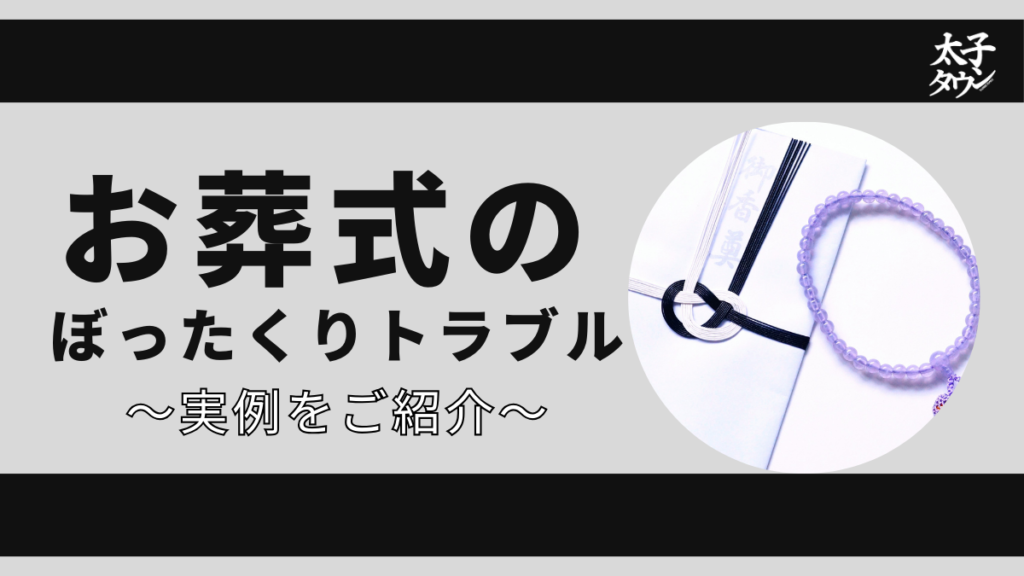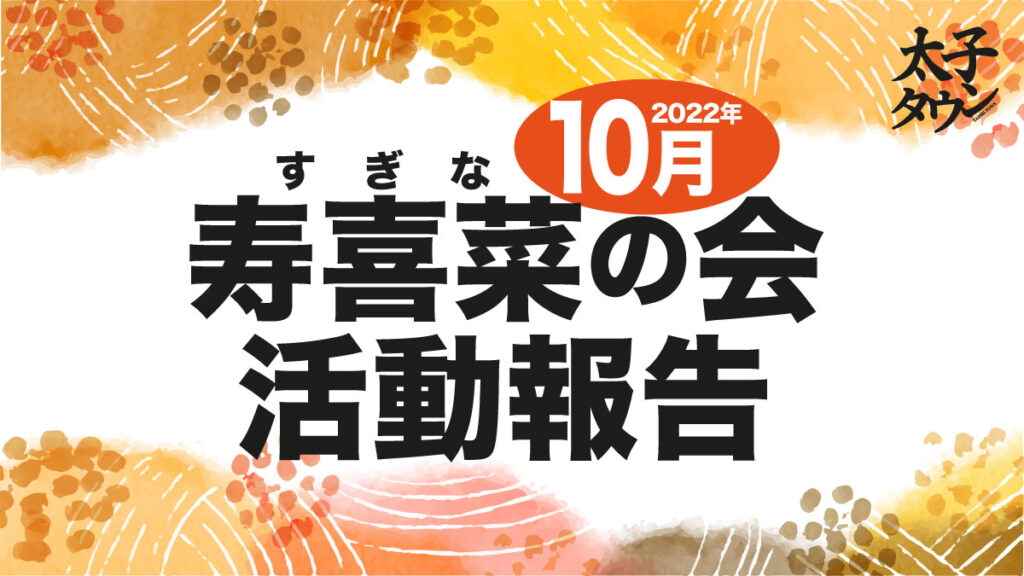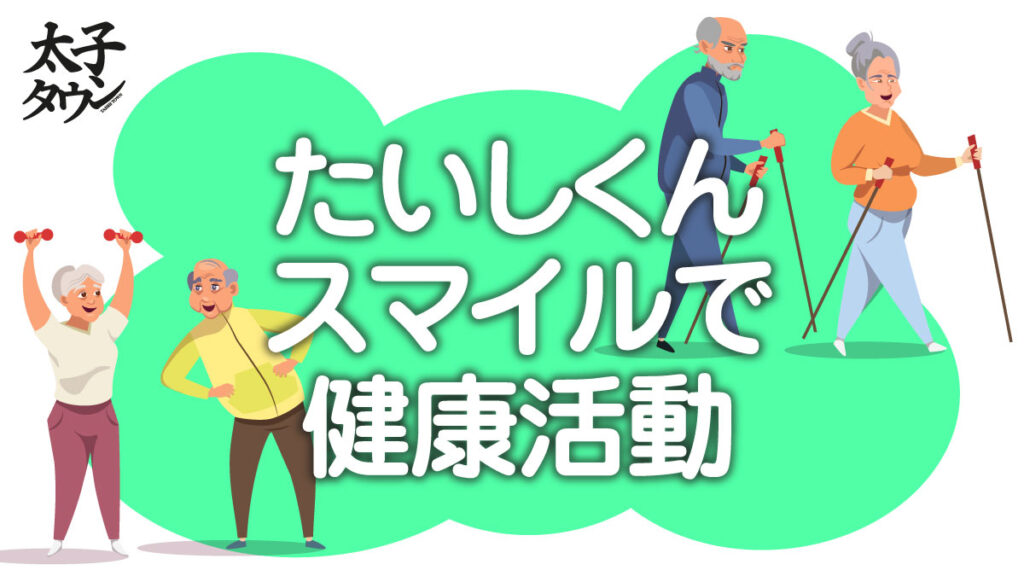ナガミヒナゲシが危険と言われる理由をご存じでしょうか。
春になるとあちこちで見かけるオレンジ色の可憐な花ですが、実は強い繁殖力と有毒性を持つ外来植物です。太子町内の通りでもよく見かける植物なので、身近な場所に潜むリスクとして注意しましょう。
太子町内でも咲いている春の危険植物

ナガミヒナゲシは現在、日本全国に広がっており、太子町内でも道路脇、空き地、公園、畑の隅などあらゆる場所で確認されています。
乾燥した日当たりの良い場所では、簡単には繁殖を防げません。
特に学校や公共施設の周辺では、子どもたちが花に興味を持って手を伸ばすことも多く、安全面からも無視できない存在です。
ナガミヒナゲシの特徴と問題点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学名 | Papaver dubium |
| 原産地 | ヨーロッパ地中海沿岸 |
| 花期 | 春(4~6月) |
| 繁殖方法 | 種子(風・動物・人による拡散) |
| 特徴 | 1年草、茎に毛、4枚の赤橙色の花弁、果実1個で数千~数万粒の種子 |
| 環境への影響 | 在来植物・作物との競合、生態系バランスを崩す |
| 駆除方法 | 根からの抜き取り、花が咲く前の処理が理想的 |
ナガミヒナゲシの種子は非常に軽く、風や人の靴底、自転車のタイヤなどによって思わぬ場所へ拡散します。
特に都市部では、わずか1年で群生地が形成されるほどの爆発的な繁殖力をもつ植物です。
その結果、もともとそこに生えていた在来の植物たちが光や養分を奪われ、姿を消してしまうことも少なくありません。
有毒性と駆除の注意点

ナガミヒナゲシは、茎や葉にアルカロイド系の有毒物質を含みます。触ると皮膚に炎症を起こすことがあり、特に子どもが誤って手にすると危険です。
駆除の際は必ず手袋を着用し、根からしっかりと抜いて、種が飛ばないよう密封して処分してください。
市販の除草剤では完全には対応できず、物理的な除去が有効とされています。
駆除のタイミングとしては、開花前や開花直後が理想です。果実が熟して種子を飛ばしてしまうと、翌年には倍以上の数に増殖することもあります。太子町内でも早めの発見・早めの対応が大切です。
行政や研究機関も注目する「沈黙の侵略」
ナガミヒナゲシは1960年に東京都内で初めて確認されて以来、急速に国内へ広がりました。
観賞用として持ち込まれた経緯があり、その美しさが逆に油断を生んでしまったと考えられています。今のところ法律では規制されていませんが、国立環境研究所のデータベースでは注意すべき外来種として取り上げられている植物です。
また、大阪狭山市や堺市、東大阪市など大阪府内の複数の自治体でも、ナガミヒナゲシに関する注意喚起を公式サイトで発信中です。
太子町としても、この問題に対して積極的な啓発と地域ぐるみでの対策が必要とされています。